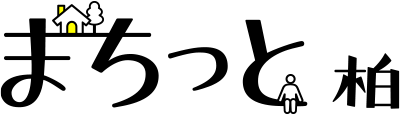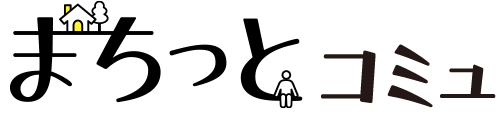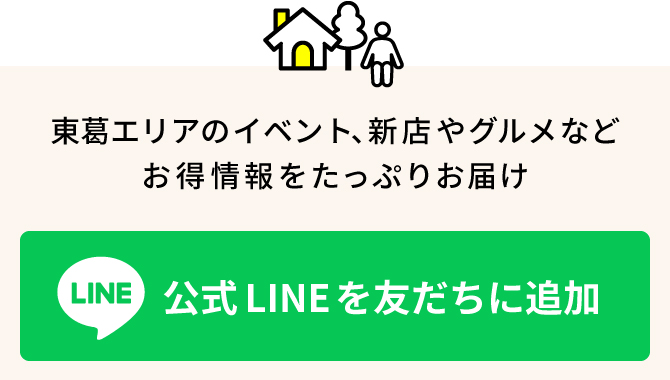こんにちは! 野草フォトクラブ19のポコです。
暑くなり、野草の撮影も命がけになってきました。
そこで今回は柏・流山・松戸でこれから見られる秋の野草の紹介をすることにしました。
本当は暑さにめげましたので・・・。
今回は「アキノノゲシ」と「キンエノコロとその仲間」、「ヒンジガヤツリ」などの様子を少し詳しくお知らせします。
アキノノゲシ(秋の野罌粟)キク科

【写真1】アキノノゲシ
〔出会うところ〕
- 日当たりのよい空き地、草地。
〔東葛飾での自生具合〕
- ほどほどに見られます。
〔主な特徴〕
- 2年草。草丈は1.5~2mと高くなります。
- 茎の色は緑色か緑茶色。茎を切ると白い汁が出ます。
- 葉は大きく、葉の切れ込みも大きい。また柔らかいです。
- 茎の上部に頭花を多数つけます。
- 頭花の直径は約2cmで、外側の舌状花はやさしい雰囲気。
〔東葛飾での花期〕
- 9~10月。花は中心が淡い黄色、周りがクリーム色。花は昼間に開き、夕方にはしぼむ。
〔性格・その行動〕
- 綺麗好き。秋の野原でキャンバスに絵を描くのが大切な時間。
〔豆知識〕
- 名は草姿がノゲシに似て、秋に花が咲くことから付けられました。
- 花の咲く前の葉は、特においしそうに見えます。ぼくは以前、味噌汁の具にして食したことがあります。でも味は・・・内緒‼
- 秋の野草の中で清々しい感じがする花の1つ。
- 春に咲くノゲシ(別名ハルノノゲシ)は街中でもよく見られますが、アキノノゲシ(本種)は野原に行かないと無理かな?

【写真2】アキノノゲシの淡いクリーム色の花弁

【写真3】アキノノゲシの葉 見た目より柔らかい葉
キンエノコロ(金狗尾)イネ科

【写真4】キンエノコロ(金狗尾)イネ科
〔出会うところ〕
- 日当たりのよい空き地、草地、田の畔、江戸川の土手など。
〔東葛飾での自生具合〕
- やや少ないかな?
〔主な特徴〕
- 1年草。草丈30~80cmになります。
- 茎の色は緑色。
- 葉は線形で、長さ10~25cm。幅は3~8mm。
- 円錐花序(穂)は長さ3~10cmで円柱状になり、穂はやや傾きます。小穂は広卵形で、長さは2.8~3mm。
〔東葛飾での花期〕
- 8~10月、穂は黄金色。
〔性格・その行動〕
- 照れ屋だが目立ってしまう。秋の夕方、買い物に行く姿がとても輝いている。
〔豆知識〕
- 名の由来はエノコログサに似て、小穂の毛が黄金色【写真5】になることから。
- キンエノコロはアキノエノコロ【写真7】が出るころに見られることが多く、場所によっては、ムラサキエノコロ【写真8】と混生して群生します。

【写真5】キンエノコロの小穂の毛
- 似たものにコツブキンエノコロ【写真6】があります。花期は8~10月で、穂の色は紫色がかった黄色。キンエノコロと比べ穂が2.5~4cmと短く草丈も15~30cmと低い。小穂は長楕円形で、長さは2~2.8mm。
- コツブキンエノコロの数は少ない。東葛飾でも自生しているがキンエノコロの小振りのものとの区別は、図鑑がないと戸惑います。

【写真6】コツブキンエノコロの穂

【写真7】アキノエノコログサの穂

【写真8】ムラサキエノコロ

【写真9】ムラサキエノコロの群生
一寸休憩 ・「肺気腫なので・・・」
肺気腫と診断されて6年になります。毎朝スビリーバという薬を2回吸入しています。
年2回肺のスキャンもします。レントゲンの映像を見ながら「この黒い所が肺のとけた部分」と専門の先生。心配なので「いつ肺癌になります?」と訊くと、素晴らしい答え。
「長生きしていればいずれね・・・」本日の診察終了。ありがとうございます…。
ヒンジガヤツリ(品字蚊帳吊)カヤツリグサ科

【写真10】ヒンジガヤツリ
〔出会うところ〕
- 水田、休耕田、田の畔、湿った低地や畑。
〔東葛飾での自生具合〕
- 少ない~稀。
〔主な特徴〕
- 1年草。茎は直立します。草の高さは5~20cm。
- 茎は細くやや円形で緑色。
- 葉は根元から多数出て、細い線形で柔らかいです。
- 小穂(しょうすい)の大きさは3~5mmで卵形をしてます。
- 花穂(かすい)の下に長い葉のような2枚の苞葉が出ます。
〔東葛飾での花期〕
- 8~9月、小穂は緑褐色。
〔性格・その行動〕
- むずかしいことは考えずにのん気に生活している。
〔豆知識〕
- 名は、茎の先に球状の小穂が3個つき「品」の字の形のように見えることから付けられました【写真11】。なるほど‼ 同定は楽、いいね!
- 株によっては小穂が2個や4個のものもあります。別名はサンカク、コメコンペト。

【写真11】ヒンジガヤツリの花穂 とても小さい
- 晴れた日の日課の野草の写真撮りでぶらぶらしていたら、偶然見つけました。流山の古間木の稲刈り後の水田にひょつこり顔を出していました。
- 花穂が球状になるカヤツリグサの仲間としては、ヒメクグやタマガヤツリ、ミコシガヤがあります。いずれも湿地に見られますよ。これらの同定もいいね。

【写真12】ヒメクグの花穂 よく見かけます

【写真13】タマカヤツリの花穂 時々出会います

【写真14】ミコシガヤツリの花穂 時々出会います
流山市古間木
★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。
※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください
この記事を書いたのは…

野草フォトクラブ19
撮影対象を山野草に絞ったちょっとユニークな写真クラブです。 東葛地区で咲く四季折々の花やその花についての楽しい説明など、発信していきたいと思います。