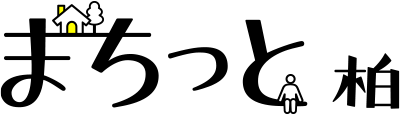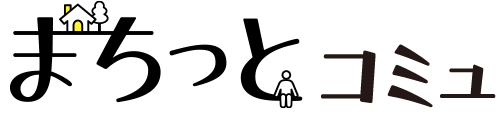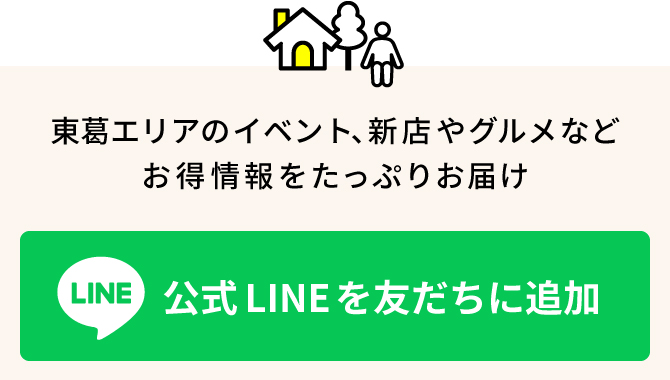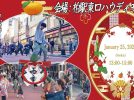こんにちは! 野草フォトクラブ19のポコです。
今回は、5月の根木内歴史公園で見かけた春から初夏の野草の紹介です。
特に今年は春~初夏の野草の入れ替わりが早いようです。
根木内歴史公園はその名からわかるように、根木内城跡の一部を公園にしたものです。
城郭の跡や空堀のほか、お堀の跡でしょうか?湿地帯が広がってます。
ここでは四季折々、湿地を好む植物が多く見られ、とても楽しいところです。
本日は、公園内の田やその周辺に見られた野草を取り上げています。
オオカワヂシャ(大川萵苣)
和名(日本での植物名)の由来は、草全体がカワヂシャに似るけれど、花や葉が大きいことから付きました。
カワジシャは川(湿地)に生えるチシャ(レタスのこと)で、食べられます。
水辺や水気の多い空き地など生えるヨーロッパ~アジア原産の多年草で、茎は直立し、草丈は30~100cmほどになります。葉には柄がなく対生します。
花は深く4裂します。淡い青紫色で、花弁の濃い紫色の筋が目立ちます。花の大きさは6~10mm。
東葛飾(柏・流山・松戸)での開花期は4~6月です。

オオカワヂシャの花(オオイフノフグリの仲間です)

オオカワヂシャ
オランダガラシ(和蘭芥子)
和名は、明治の初めに野菜として日本に来た事と、食べると辛味があることから付きました。
オランダ原産ということではなく、外国、特に西洋から来たものに「オランダ」を付けたまでです。
別名はクレソンで、このほうが知名度は高いかな?と思います。肉料理のつけ合せの野菜の1つになっています。
水辺や池の縁に生えるユーラシア原産の多年草で茎は直立します。草丈は30~50cm。葉は複葉で小葉は3~11枚つきます。
花は白色で、よく見るとタネツケバナの花に似ています。花弁は4枚の十字形の花で、多数つき、大きさは6mmほどになります。
東葛飾(柏・流山・松戸)での開花期は4~5月です。

オランダガラシ 別名はクレソン こちらの方が有名です 美味しいね

オランダガラシ(クレソン)の花は4枚の十字形
ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)
和名は、花の様子を鳥の鷺(さぎ)に見立て、色が紫色であることから付けられました。
明るく、日当たりの良いやや湿った空き地や草地に生える多年草です。
茎は地を這うように伸び、草丈は10~15cmほどです。花は唇形で、大きさは1.5~2cmになります。花の色は淡い紫色~濃い紅紫色でよく目立ちます。
よく似た仲間に白い花のサギゴケや花や草姿が小型のトキワハゼ(次項)があります。
東葛飾での開花期は4~5月です。

ムラサキサギゴケ 今が旬のようで群生しています。

ムラサキサギゴケの花。大きさ1.5~2cm。花は淡い紫色で黄色の斑点が多く見られます。トキワハゼとよく似ているので、慣れないと間違えます。
トキワハゼ(常盤爆)
和名は、ほぼ1年中花が見られ(常盤)、果実がはぜることから付きました。
やや乾いた空き地や道端、畑などに見られる1年草でムラサキサギゴケに似ています。
草丈は5~20cm。根ぎわの葉は対生し大型になり、上部の葉は小さくなります。花は長さ1cmほどの唇形で、淡い紫がかった白色でムラサキサギゴケより小さいです。
東葛飾での開花期は4~10月で、花の時期が長いのが特徴です。

トキワハゼは、ムラサキサギゴケより色白です

トキワハゼの花。大きさ約1cm。ムラサキサギゴケの花より小さくおとなしい感じです。色は白っぽく黄色の斑点が少ない。
チガヤ(千茅)
和名は穂が多く、群がり生える姿から千のカヤ(茅)と見なしてつけられました。別名はチバナ、ツバナ。
野山の日当たりのよいやや湿った草地、空き地、道端に群生して生える多年草です。
草丈は30~60cmで、白色の長い毛か密生した円柱形の穂をつけます。根茎の白い部分は、漢方薬や民間薬で利尿用として使用されています。
東葛飾での開花期は4~5月で、白い綿のような穂の長さは10~15cmになります。

チガヤ

チガヤの穂(長さは10~15cm)。左の穂には茶色の葯(少し時間がたった雄しべの葯)が、右の穂には紫色の葯(若い雄しべの葯)が見られます。雄しべと雌しべが落ちると銀白色の綺麗な穂になります。この頃触るとふわふわ感が楽しめます。
ヘビイチゴ(蛇苺)の果実
普段食べているイチゴは花床(かしょう)という膨らんだ部分で、果実ではありません。果実は、花床の表面に付いている多数の粒々がそれになります。
下の写真は花床と多数の果実で、果実にはしわが多く見られます。これが他のヘビイチゴの仲間との違いです。
花床と果実は毒ではありませんが、美味しくありません。味の付いていない麩(ふ)のようで、食感はパフパフしています。
試したい方は、よく洗ってチャレンジしてみてください。

花床と多数の果実

ヘビイチゴの花。似た仲間にヤブヘビイチゴがあります。花床は約2倍の大きさになります。ヘビイチゴよりも食べ応えがありますよ。
カキドオシ(垣通し)
和名は花後に茎がつる状になり、垣根を通りぬけるように伸びることから付けられました。
別名のカントリソウは子どもの癇(かん)を取る薬になることからつきました。生薬名は連銭草(レンセンソウ)で湿疹や子どものひきつけ、夜泣きに使用しました。
根木内歴史公園では、今この花が旬のようです。淡い紫色の唇形の花が輝いていました。

カキドオシの花 上から見ると可愛いいよ
5月の根木内歴史公園

5月の根木内歴史公園の様子
根木内歴史公園
★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。
※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください
この記事を書いたのは…

野草フォトクラブ19
撮影対象を山野草に絞ったちょっとユニークな写真クラブです。 東葛地区で咲く四季折々の花やその花についての楽しい説明など、発信していきたいと思います。