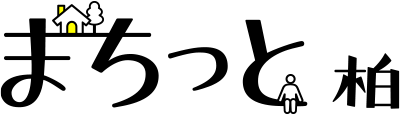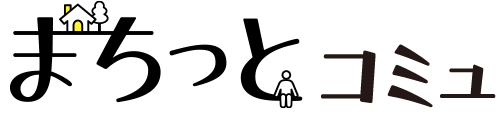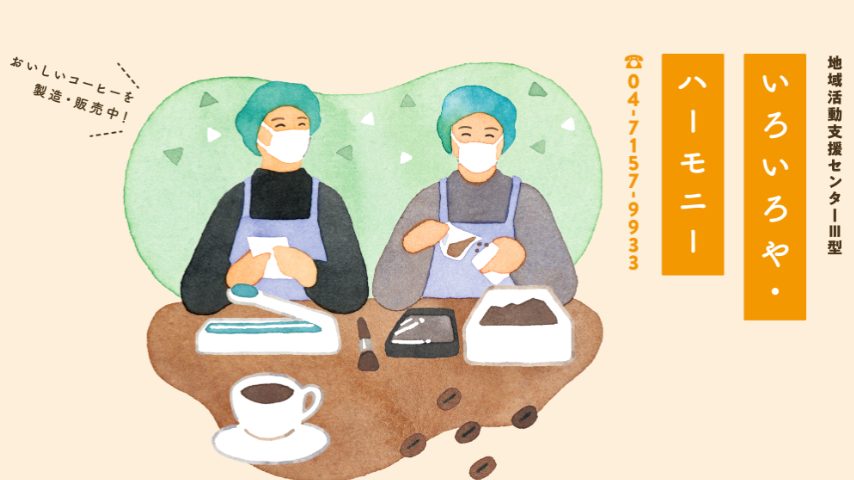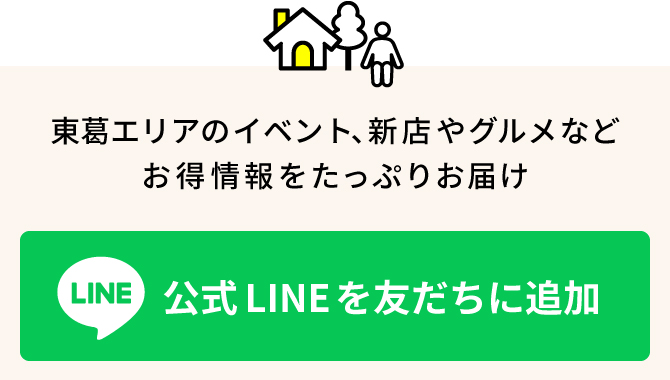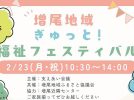こんにちは!
生まれも育ちも流山、スペシャリストのスガコウタロウです。
今回は流山に昔からあって誰もが知ってる和菓子司 藤屋の志賀さんのお話です^^
はじめてお会いした瞬間から、時間が前後しても同じ人が話している… そう感じた。
中学生で「菓子の道に進む」と決めた青年、修行場で鍛え上げた青年、店を一人で回す今の職人。
その年齢に“タイムスリップ”しても、芯はぶれない。
志賀さんは、いつでも志賀さんだ。

その起点は、家業の強制ではない。母方のおじいさんが「誰も継がなかった」仕立て屋の無念をぼやいた言葉。それが彼の責任感に火をつけた。誰かの未完を受け止め、自分の意味に変換する。中学時点で進路を決め、高校は商業に進み、簿記や経済の基礎を固める。
卒業後は横浜・川崎などで十年に及ぶ修行へ。「すぐ家に入らず、まず外で学ぶ」決意を感情の勢いで消費せず、人生設計に翻訳する思考の高さがここにある。
修行の途中、父の病で店は一時閉店。彼は戻る決断をする。ただ戻っただけではない。店内の動線から工場機能まで、一人で回し切るために構造を作り替えた。ショーケースを引き、奥の作業効率を上げ、品目は段階的に増やす。戦略は「維持」ではなく「再設計」だ。

味の核心はもっと明快だ。よくある「機械は使いません」という情緒ではない。「機械を使うと出ない味を出すために、使わない」のである。
丸く均質な団子玉を量産する機械は、生地を “ 機械に合わせる ” ことを迫る。やわらかさを犠牲にしてでも流れ作業に乗せるのが前提になる。
志賀さんはそれを拒む。生地は手で切り、手で丸め、串を打つ。手間は増えるが、求める舌触りふわっとして、のど奥で軽くほどける滑らかさはそこでしか立ち上がらない。
一方で、理想主義者では終わらない。
朝生の団子・大福は日内完結で出す一方、冷凍技術や日持ちの工夫も躊躇なく採用する。
目的は「毎日うまい」を切らさないこと。
手でしか出ない味は手で、科学で安定するところは科学で。方法は信仰ではなく手段。そこに迷いがない。

価格観にも、職人の倫理が通っている。
ここは江戸川台。観光地でもデパ地下でもない。
だから「江戸川台の価格」であることを守る。材料は東京の老舗と同じ銘柄を指定して妥協しないが、家賃や余計な経費がかからない分は、お客さんの “ 毎日の手の届く範囲 ” に還元する。将来の改装資金や雇用拡大といった “ 大義名分 ” で上乗せする誘惑は、彼には関係がない。見ているのは、目の前の一人のお客さんの今日の一口だ。
経営の現実は厳しい。材料調達は年々難しくなり、米粉の産地配合を検討する局面もある。最低賃金や後継者不在の波が、町の和菓子屋の存続を揺らす。けれど志賀さんは、問題を “ お題目 ” にしない。できる配合で最良の味を、できる価格で、今日も出す。それだけだ。そこにエゴはない。あるのは、役割の自覚と、継ぐと決めた人間の矜持である。

この店が “ 地元で愛されている ” ことは、もう説明の要らない事実だろう。だが私は、なぜ愛されるのかを今日、はっきり見た。
中学生の決意を、生涯の設計図として書き換えずに持ち続ける人間。その設計図に沿って、技術・動線・価格・仕入れまで現実に落とし込む職人。そして「機械では出ない味」を理由に手を選び、「毎日うまい」を理由に技術も使う矛盾のない倫理。
年齢が変わっても、状況が変わっても、 “ 志賀さんは志賀さん ” 。この和菓子のおいしさは、配合や火加減の前にこういう人間からしか立ち上がらない。
志賀さんは最後に「私のように日本には誇りをもって頑張っている名もなき和菓子屋が沢山あります」と語りました。
日本には、このように長い歴史と深い文化を背負い、静かに技を守り続けてきた職人たちが数えきれないほど存在します。私たちは、その存在を決して忘れてはならず、未来へとつないでいく責任を背負っているのです。


和菓子司 藤屋
★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。
※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください
この記事を書いたのは…

おおたかの森ファームスガコウタロウ
東京工業大学工学部を卒業後、工業デザイン事務所にてデザイン業務を経て、家業である税理士事務所に入社。そのノウハウを生かし経営コンサルティング おおたかの森ファーム株式会社 を設立。ボクシング好きの三児の父。