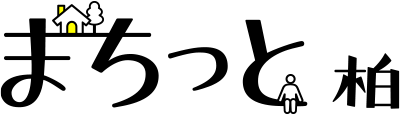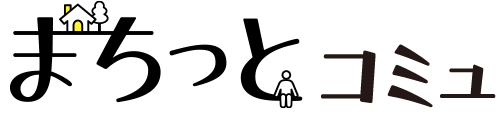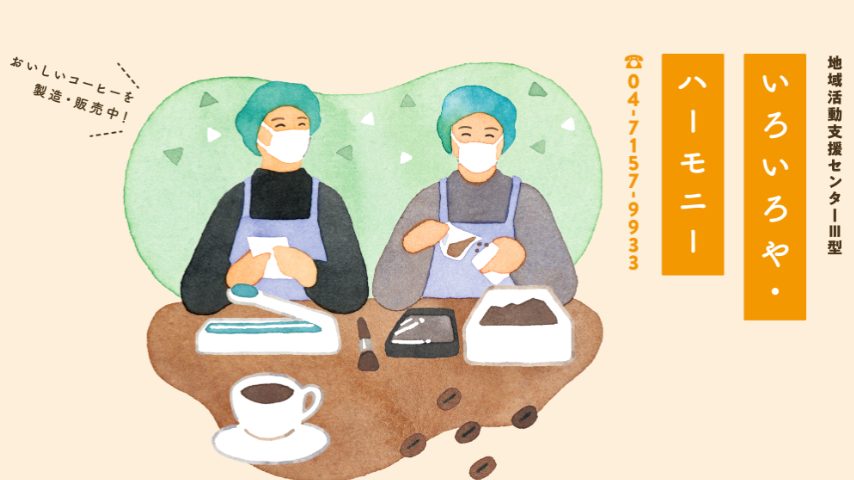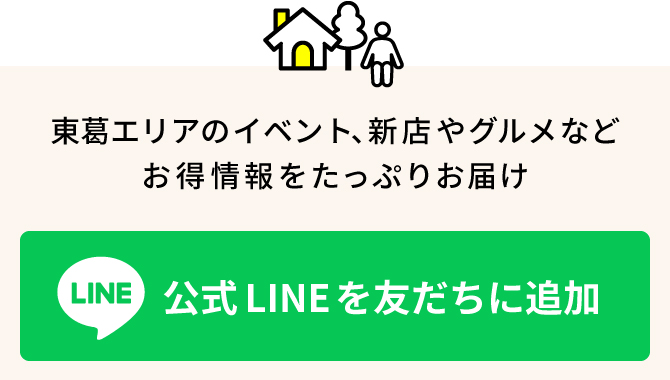こんにちは!
生まれも育ちも流山、スペシャリストのスガコウタロウです。
私は現在、流山市おおたかの森の自治会で副会長を務めています。
正直に言えば、役職に就くまでは自治会の活動内容を深く知る機会は多くありませんでした。
しかし副会長となって初めて、「納涼祭」という地域にとって大きな行事の存在を知り、その意味の大きさに気づかされました。
納涼祭は、単なる夏のイベントではありません。
自治会が中心となって準備を進める中で、会長が地域内外に挨拶に回り、他の自治会や地域団体ともつながりを深める大切な機会でもあります。
模擬店や子ども向け企画など表舞台に立つ催しの裏では、多くの人が力を合わせ、汗を流しています。
その姿を目にして初めて、自治会の活動とは、地域の生活の目に見えない基盤を支えているのだ」と実感しました。

事業承継の難しさ
こうした大きな行事や日々の活動は、長年にわたり地域を支えてきた先輩方の奉仕と経験の積み重ねによって成り立っています。
しかし一方で、そのやり方や感覚は若い世代にとっては馴染みのないものでもあります。
効率や費用対効果を重視する世代からすると「なぜここまで労力をかけるのか」と疑問に思うことも少なくありません。
この感覚のズレを解消しないまま世代交代を進めると、お互いに不満が溜まり、時には衝突を生みます。
その延長線上には、自治会そのものが崩れてしまうリスクさえあります。

学び合いが前提
だからこそ必要なのは「学び合い」です。
ベテラン世代は、「若い人が初めて自治会に触れている」という現実を理解し、押しつけではなく “ 伝える ” 姿勢を持つこと。
若い世代は、「自治会は商売やサービス購入とは異なる共同体の仕組み」であることを知り、効率だけでは測れない価値を学ぶこと。
この相互理解がなければ、自治会の事業承継はうまくいきません。

一歩を踏み出すために
学び合いといっても、大げさな仕組みは不要です。
活動内容や収支をわかりやすく “ 見える化 ” すること、小さな役割を分担して少しずつ引き継ぐこと、そして怒りや不満を爆発させずに「収める」意識を持ち合うこと。それらの積み重ねが世代交代を無理なく進める力になります。
納涼祭を通じて私が学んだのは、自治会は単なるイベント運営団体ではなく、「地域の暮らしを支える共同体」であるということです。
そして、その共同体を次世代へとつなぐためには、何よりも学び合いの姿勢が前提になるのだと強く感じています。
おおたかの森ファーム株式会社
★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。
※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください
この記事を書いたのは…

おおたかの森ファームスガコウタロウ
東京工業大学工学部を卒業後、工業デザイン事務所にてデザイン業務を経て、家業である税理士事務所に入社。そのノウハウを生かし経営コンサルティング おおたかの森ファーム株式会社 を設立。ボクシング好きの三児の父。