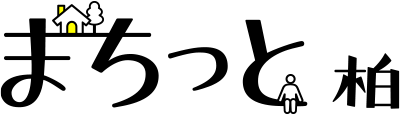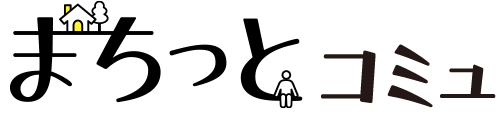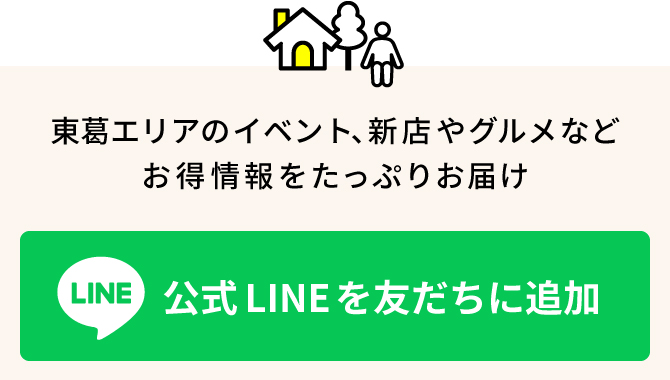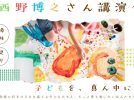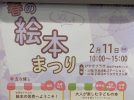こんにちは、流山市在住2児の母 まちっと柏編集部のtoriemaです。
2月11日(月・祝)に行われた工藤勇一氏による
「未来を創る子ども達 共に育む生きる力フォーラム」へ行ってきた感想をお伝えします。
工藤勇一氏の教育改革は、宿題ゼロ・定期テストなし・固定担任制や校則の改廃など様々な学校の常識を覆すスタイル。
これまで、千代田区立麹町中学校 や 私立横浜創英中学校・高等学校の校長に就任し、
そのスタイルを取り入れた教育を行ってきました。
わたしは特に「宿題なし・定期テストなし・校則なし」のワードがとても気になりました。
なぜ、なしにしたのか、その背景が講演を聞くと分かってきました。
まずは日本の問題を知ろう
まずは、日本で何が起きているか整理していきます。
現在全国に不登校児の数は34万人超いると言われています。
いじめ問題はとても深刻化しており、小中高生が自ら命を断つ件数は527人。
年々増え続ける学校・教育問題。
《何を変えたらこの問題は解決できるのか?》
これまで教育現場の最前線に立ってきた工藤勇一氏はこう語る。
《世界的に見ても日本の子どもたちは幸福度が低い。
ただし、学校教育の中で「主体性」を育むことができれば、子どもたちは世界に通用する立派な大人になるだろう。》
さて、工藤勇一氏の言う「主体性」とはどういう意味なのでしょう?
「自主性」と「主体性」どっちが大事?
みなさんは、「自主性」と「主体性」の違いが分かりますか?
わたしも講演を聞くまでは両者はとても似ている言葉だと認識していましたが、全く別物であることが分かりました。
自主性・・・決められたことを率先して行う
主体性・・・自分の頭で考えて判断して行動する
ということなのです。
似ているようで意味はまるで違いますね。
現在の日本の教育は「自主性」の中で育っていると言われています。
「主体性」を育む教育はどんなものなのでしょう?
工藤勇一氏はたった3つの言葉を子どもにかけてあげるだけで、別人に変わると言っています。
主体性のある子どもを育てるには?3つの魔法の言葉
「主体性」を育むには、子どもたちに3つの言葉をかけてあげましょう。
・どうしたの?
・きみはどうしたいの?
・何を支援してほしいの?
これだけで子どもたちは自ら考え行動に起こしていくそうです。
そんな簡単なことでいいの?
と思った方もいるかもしれませんが、
この言葉を使っても「主体性」がない子どもたちはとても混乱するそうです。
それもそのはず。大人たちがそういう子どもたちを育ててしまった結果であり、まずはその現状を受け止めてあげていかなくてはいけません。
学校を変えることは簡単ではない
工藤勇一氏はこれまで千代田区立麹町中学校、私立横浜創英中学校・高等学校の改革を進めてきました。
そこで少し気になっていたのは、ニュースで千代田区立麹町中学校の校長が変わってから、また今までの教育方針に戻ったと言う点。
この点は講演会のときに少し触れられていましたが、
1つの公立学校を変えようとしても、年度で先生の入れ替わりがあるためなかなか統制が取れず、
校長が変わればなお、学校の方針が一から変わることも起きるため改革をするのはとても難しいのだそう。
教育長が宣言!流山市全体でやりましょう
今回の講演会は2部制で行われており、2部はパネルディスカッションを行いました。
また2部が始まる前に、予定にはなかった千葉県知事の熊谷俊人氏が挨拶にいらっしゃいました。
このイベントがあると聞きつけて、駆けつけてくださったそうです。
パネラーは、工藤勇一氏、流山市教育委員会 吉田瑞穂氏、流山市立おおぐろの森中学校校長 前川秀幸氏、みらいのたね応援団代表 良峰 武徳氏が登壇。
流山市立おおぐろの森中学校では、
一足早く「校則なし、夏休み・冬休みの宿題なし、チョークをほとんど使わない授業」を実践されている学校です。
各々が学校教育についてアツいトークを繰り出す中、
吉田教育長は『流山市全体で工藤勇一先生の教育方針を取り入れましょう』と発言。
会場も驚きと、期待で少し沸いていました。
1つの学校で取り組むだけでは実りがないと言うことを工藤勇一氏も言っていただけに、流山市全体で教育改革を進めるのはとても意味のあることです。
市をあげて取り組むのは流山が初なのかな?と思いきや、
もうすでに兵庫県と広島県は県をあげて工藤勇一氏の教育を取り入れているのだそう。
となれば、これからも別の市や県が工藤メソッドを取り入れる日は近く、
その中でも流山市は教育改革の最先端にいる街であるのはとても期待できるのではないでしょうか。
講演会に参加してどうだった?
講演会に参加したときに、市民活動団体リプル流山の方とお話しをする機会がありました。
リプル流山は、子供の発達に疑問を抱える親たちが集まった団体で、発達の不安を抱える子供たち、また、その子供を持つ親たちが孤立することなく、学校や地域情報の交換をしています。
実際に参加してどうだったかコメントをいただくことができました。
自主性と主体性の話など、とても感銘をうけました。私も2児の子供を育てる親として、子どもたちになるべく自分で選択させるように心がけています。
自己選択したものには自ずと責任が生まれるからです。
自分の人生を豊かにできるのは、他の誰でもなく自分であると思っているのでなるべく主体性をもって生きてほしいと願っています。今、流山市内は子どもの増加とともに発達障害やグレーゾーンと言われる子どもも増えています。
支援級ではなく、普通級に通っている子どもも多いです。
私の子供のひとりもいわゆるグレーゾーンと呼ばれるところに入り普通級にいます。学校でも働き方改革が叫ばれている昨今、全てを先生たちに求めるのではなく、適材適所で人材を置くために療育施設などに外部委託をして実践経験を持つ先生たちの手を借りられることができれば先生の働く環境も良くなると思っています。
日本の学校はクローズな部分もまだまだ多く、なかなか変えていくのは難しいとリプル流山会員さんたちの話を聞いても思う部分はありますが、子供は未知数で多くの可能性を持っている存在です。
いかなる子どもでも真の意味での学びの場として、学校の存在があってくれたらと願わずにはいられません。流山市の教育長も市全体で工藤先生のメソッドを取り入れようとしてくださるところに驚きつつも、ワクワクしたところがありました。
ぜひ流山市の教育は、子どもたちが学校に行くことにワクワクする学びの場としてあってくれたらいいなと思いました。リプル流山代表 花岡さん
工藤先生の講演会に参加して、心に響いた言葉がいくつかありました。特に、「みんな仲良く」「挨拶がきちんとできる子」という理想論が子どもたちに押し付けられている現状についての話は、とても考えさせられました。
子どもたちは、周囲の友達や学校の雰囲気に敏感です。「みんなと仲良くしなければ」「挨拶をしっかりしないと」といった期待に応えようとするあまり、自分を隠してしまうことがあるのではないでしょうか。
また、自分の気持ちを正直に表現する子どもが「悪い子」と非難されてしまう構図にも、戸惑いを覚えます。講演の中で、工藤先生が指摘した通り、学校は理想的な環境を目指すあまりに、教員も子どもたちも疲弊して悪循環に陥っているのが現状なのではないか。
子どもたちが主体的に考え、行動できるように促すためには「どうしたいの?」と問いかけることで、少しずつ変わる可能性があるというお話が印象に残りました。また、現実的には大学が今後10年間で600から200校へ激減するだろうと予測もされ、試験もAO入試に移行していて、何もしなくても教育システムは崩壊するのだと説明してくださり、目から鱗でした。
後半のディスカッションでは、流山市が今後180度教育を転換していくという内容を聴けて、非常に嬉しく、感動しました。
私自身もこれまでの学校の常識を見直し、アップデートしていく必要があると感じましたし、学校が柔軟性を持ち、子どもたちの個性や意見を尊重してくれる未来を心から願っています。リプル流山 Iさん
花岡さん、Iさんコメントありがとうございます。
これからの流山市はどうなっていく?
さて、吉田教育長からの宣言があった一方でこれからの流山市がどうなっていくのか気になりますよね。
その点深掘りをすべく、今後みらいのたね応援団代表 良峰 武徳氏へ色々聞いてみたいと思っています。
2月24日(月・祝)は、誰1人取り残さない教育を実践した校長先生、木村泰子氏をお呼びした講演会も実施。
どんな会になるのか楽しみですね!!
次回の更新も楽しみにお待ちくださいませ。
▼木村泰子氏 講演会の詳細
【流山市】誰1人取り残さない教育を実践した校長先生!木村泰子氏登壇 【ぶっちゃけトーク】2/24(月•祝)開催!
▼みらいのたね応援団の詳細
未来を担う子どもたちの「たね」を育てるサポートチーム、それが【みらいのたね応援団】
この投稿をInstagramで見る
みらいのたね応援団 Instagram
流山市教育長 Instagram
リプル流山 Instagram
★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。
※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください
この記事を書いたのは…

まちっと編集部toriema
流山市在住、2児の母。 子育てをしながら感じた「これ知りたかった!」を大切に、流山・柏・松戸エリアの子連れで楽しめるイベントや、暮らしに役立つ情報を実体験を交えて発信しています。